
わが家には3人の子供がいます。
今日は7歳になった次女のお話です。
次女がADHDと診断された日から5年が経ちました。
診断を受けた当時は、不安と混乱で頭がいっぱいでした。
これからどうすればいいのか、目の前が真っ暗で『娘は幸せになれるのだろうか?』と未来に希望を持てず、絶望感に押しつぶされそうだった自分を今でも鮮明に覚えています。
しかし今では漠然とした不安から解放され、娘なりの成長に喜びを感じる毎日です。
5年たった今、当時のことを振り返りたいと思います。
今、診断を受けたばかりで、目の前が真っ暗になっているお母さんへ。



5年前の私もそうでした。
でも、大丈夫。その理由を今からお伝えしますね。
ADHDと診断された当時のこと


ADHDと診断を受けた頃の娘
当時、娘は2歳になっても意味のある発語がほとんどありませんでした。
しかしネットでは「3歳から突然話し出す子もいる」という情報もあり、あまり深刻に考えることはありませんでした。
しかし娘が2歳になった頃、主人が「発達検査を受けよう」と市の相談窓口に連絡したのです。
元々あまり目が合わないなど気になっていたようで、突然のことに私は驚きと怒りを感じました。
今思えば、自分に不都合なことを直視できていなかったのだと思います。



さらに2歳上の長女がかなりの多動で手を焼いていたので、次女の問題はかすんでいました。
当時は『発達障害』や『多動症』という言葉自体も知らなかったんです。
診断を受けた時の状況
2か月後、市の発達検査を受けた結果、認知能力や社会性が年齢相応の基準には達していないことが分かりました。
ですが、まだ小さいとの理由で様子を見ることになり、発達に不安を抱える親子が一緒に通える教室や相談会に定期的に参加することになりました。
しばらくして何度目かの相談会で、たまたま集団検診のために居合わせた小児発達の専門医に診ていただく機会がありました。
診察室に入り、5分も経っていなかったと思います。
娘は椅子をくるくる回したり、診察台によじ登って飛び降りようとしたり、いつも通り落ち着きがありません。
先生にも興味がないようで見向きもせず、私からも離れて部屋の奥へ行ってしまいます。
それを見ていた先生から突然「発達障害ですね。多動です。ADHDです。後日、改めて病院に診察に来てください。」と告げられました。
私は何度も「発達障害? ADHD? 確定ですか? 」と聞き返しましたが、「間違いありません。」と。
さらに「普通は2歳にもなるとお母さんの側を離れず待つことが出来るんですよ。」と言われ、私は何も言えずそのまま診察室を後にしました。



この時は「いやいや2歳なんてこんなもんでしょ!」と思ってました。
なんせ長女がこれを上回る多動だったので。
当時の私の気持ち
発達障害は、基本的には医師でなければ診断できないと発達検査の時に聞いていました。
このまま様子見をしていれば、そのうち話し出して何も問題はなくなると思っていたのに・・・。
たまたま居合わせた医師が、たった5分娘を見ただけで発達障害と診断するなんて!
だって、寝返りもハイハイも、立つのも歩くのも早かったんです。
よく寝てよく飲んでよく食べて、話さない以外育児で困ったことなんてほとんどなかったんです。
目の前が真っ暗になり、信じられない気持ちでいっぱいでした。
到底受け入れられるものではありませんでした。



今思えば診断がつくことを怖がって、娘のためにはどうするのが1番かを考えられていなかったと申し訳なく思います。
療育やサポートへの戸惑い
診察室から出るとすぐに、発達外来への受診や療育を始めるための手続きについて説明を受けました。
まだ気持ちの整理もついていないのに、本当に病院への受診や療育なんて必要なの?
そんな所に行ってしまうと、娘は本当に障がい者になってしまう。
気持ちは全く前向きではなかったものの、進められるがまま手続きを行いました。
療育先へ見学に行った際には、娘の今後が不安だと泣いてしまい職員の方を困らせました。



無知が故に偏った考えだったと反省しています。
とにかく誰かに「娘は大丈夫!」と言ってほしかったです。
夫の反応
娘がADHDと診断されたことを報告した時の夫は、とても淡々と受け入れているように見えました。
取り乱す私とは対照的で、「娘にとって1番いい選択をしていこう」と療育などにも前向きな様子です。
また「診断を受けたからと言って、何かが変わる訳ではない。診断前も診断後も娘は変わらない。」と言っていました。
けれど私にとっては世界がひっくり返る出来事だったんです。
そこまで簡単に割り切れるものなのか?と当時の私はなんだか冷たく感じてしまっていたと思います。
しかし少しずつ、夫の言った言葉の意味が理解できるようになっていきました。



娘が早い段階で療育や病院と繋がれたのは、間違いなく夫のおかげです。
ADHDと診断されてから5年が経って今思うこと


早い段階で療育に通えて良かった
診断を受けた当時は「本当に療育が必要なのか?」と戸惑う気持ちが強かったのですが、結果的には早い段階で療育に通えたことは娘にとっても、私にとっても良かったです。
療育では少人数制や個別対応してくれるところが多く、1人1人に目が行き届くので、娘の特性に合わせたサポートをしてくれます。
また、心配していた幼稚園入園前に、集団の中での過ごし方を学べたことも良かったです。
さらに、家庭では気づかなかった娘の得意・不得意が見えてきたことで、どのような接し方が良いのかを学ぶ機会にもなりました。
親として「どうしてこんな行動をするんだろう?」と悩むことも減り、娘を理解しやすくなったと感じます。
相談先ができて良かった
診断を受ける前は、娘の行動や周りとの違いに不安を感じても、誰にも話せず1人で抱え込んでいました。
しかし、療育や病院と繋がることで、専門家に定期的に相談できるようになり、「こういう子もいるよ」「こういう対応をするといいよ」と具体的なアドバイスをもらえるようになりました。
何より、娘の特性を理解してくれている方々に、漠然とした不安や悩みを聞いてもらえることはとても有難く、何度も救われました。
私には、子供の発達についてや、心の内を話せるママ友や友人はいません。
なので、話を聞いてもらえる場所ができたことはとても心強かったです。
発達障害について理解が深まった
診断を受けた当初は、「発達障害」と聞くだけで不安になり、どこかで「普通になってほしい」と思っていた部分もありました。
しかし、発達障害について学び、娘の特性を知ることで、「普通を目指すのではなく、娘に合った環境を整えることが大切なんだ」と考え方が変わりました。
このように考えることで、気持ちにゆとりを持って子ども達と接することができるようになりました。
そして「できないこと」よりも「できること」に目を向け、娘ならではの魅力や強みを伸ばしていけるようにサポートしていきたいと思えるようになりました。
漠然とした不安が少しずつなくなった
診断を受けたばかりの頃は、「この先どうなるんだろう?」と未来に対する漠然とした不安に押しつぶされそうでした。
けれど、療育や病院と繋がり、娘の成長を見守る中で、「将来が暗いわけではない」と思えるようになりました。
娘は娘なりのペースで確実に成長しているし、できることも増えています。
たとえ苦手なことがあったとしても、それを補う方法はいくらでもあるし、娘に合わせたサポートをしていけばいい。
もちろん、今でも心配事や大変なことはありますが、あの頃のような絶望感はありません!
不安でいっぱいだった5年前の自分に、「私も娘も毎日楽しく過ごしてるよ」と胸を張って言えます。
そして、誰かに言ってほしかった「娘は大丈夫!」という言葉を、あの頃の自分に伝えたい。
次女の診断、そして3人の育児。
当時の私は、目の前の命を守ることに必死で、周りのママたちと交流する余裕なんて1ミリもありませんでした。
誰とも深く仲良くなれない自分に戸惑った時期もありましたが、今振り返ると「あの時の私にはママ友はいらなかった」と心から思えます。
私が「ママ友ができない・いなくて辛い」時期をどう受け止め、どう楽になれたのかは、
👉 ママ友ができない・いなくて辛いあなたへ|ワンオペ3人育児でも楽しく子育てできた理由
【3人育児】次女が2歳でADHDと診断されました まとめ
次女がADHDと診断されてからの5年間は、不安や戸惑いの連続でした。
診断当初は受け入れられず悩む日々でしたが、療育や専門家のサポートを受けながら、少しずつ娘の特性を理解し、前向きに向き合えるようになりました。
診断は「娘に合った育て方を見つけていくスタート」だったのだと、今では思えます。
そして娘の成長を実感し、何より「この子はこの子のままでいい」と心から思えるようになりました。
もし今、診断を受けて不安な気持ちでいっぱいの方がいたら、「焦らなくて大丈夫」と伝えたいです。
悩みながらでも、一歩ずつ。わが子にとって最善の道を、見つけていけたらいいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
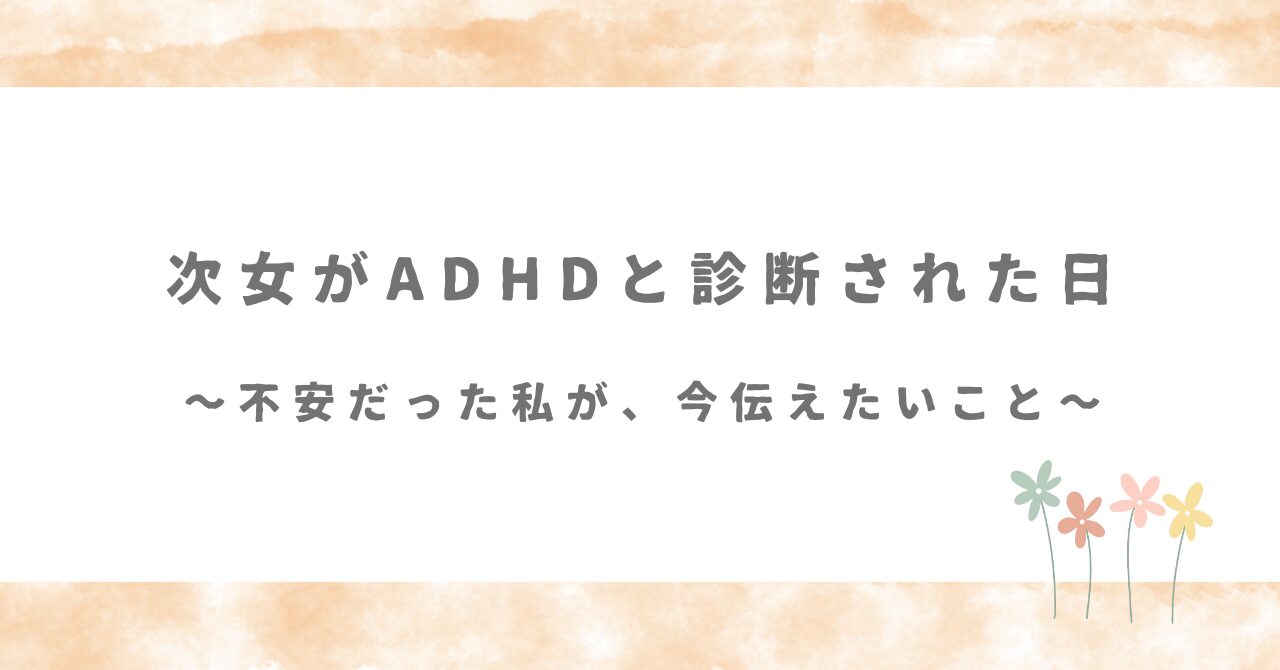
コメント